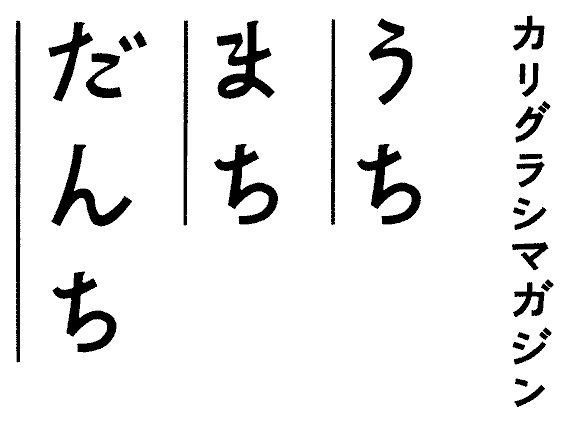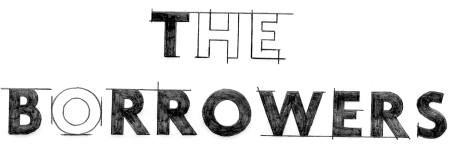西尾:音についても伺いたいのですが、劇中で音を出す機械が古いカセットデッキであったり、古いラジオだったりと、わりと音質の良くない機器で、くぐもって聞こえるようなものが出てきます。
清原:たぶん、趣味的なところが強い気がします。けど、音楽って本当は触れられないもの、形のないものだけど、それに形を与えているものにすごく惹かれるのかな。デジタルレコーダーやMP3とかじゃなく、何か形として部屋にどんどん溜まっていく、記憶を物質化してるという感じの方が面白いと思ったんです。
西尾:清原監督はデータというものに対して懐疑的なんですか?
清原:うーん、自分もデジタルで映画撮っているので、ある意味めちゃめちゃデータに頼っている。信頼してないとできないから懐疑的ではないと思うんですけども、やっぱりデジタルが普段多いからこそ、何かそういう触れるものっていうか、物質としてあるものの重要性を感じるのかな。
西尾:監督はレコードで音楽を聴くタイプですか?
清原:そうですね、レコードで音楽を聴きますね。『ひとつのバガテル』の撮影に使っていたのは「名曲喫茶ライオン」という喫茶店で、そこでずっと私、アルバイトをしていました。クラシックを本格的に好きになったり、レコードで音楽を聴くようになったのも、ライオンでアルバイトし始めてからです。レコードって物質であるがゆえに劣化してくるんですけど、何度も聴いていくうちに傷みたいなものが増えて、ノイズが増えていったりして。でも、それもまぁ一種の記憶、刻まれた記憶っていう感じがして、それも含めて楽しんでいます。

西尾:この映画『わたしたちの家』って、どこかホラー的な感触もあるんですけども、でも、ホラー映画としては作られてなくて、「気配」を描こうとしているのかなって。くぐもった音が隣りの部屋から聞こえてくる。見えないものの気配を音で感じるってことありますよね。
清原:私が住んでいるのは、メゾネットタイプの2階建ての一軒家がいっぱい横につながって並んだ、不思議な建物なんです。基本的には一軒家だという頭で暮らしているからあまり隣りを意識しない。でも、建物としてはひとつの建築物の中に縦割りでつながってるので、時々、隣りから音が聞こえてきて、たぶん、おなじ間取りなんだろうなとか想像したり。隣りに全然違う世界がある、それもまた平行世界のような感じがして。隣りの音のようなものが聞こえてきた時にだけ、それを意識しますね。
西尾:その話、監督の根っこのような気がします。普段は意識してないけども、ふとした時に隣りに誰かいるというか。さっき仰った「確固たる世界があると信じない」って言うことにつながっている。監督は幽霊的な存在についてどう思いますか?
清原:幽霊の世界もこちら側と変わらないというか。こちら側があってあちら側があるというのではなくて、自分も誰かにとっての幽霊かもしれないという感覚がありますね。普段は、自分たちを起点にして見てるけれど、反対側の世界にいる人たちはその反対にあるこっちの世界のことを幽霊と同じように見ている感じがします。
自分たちの世界はリアルで、そこによくわからないものがやってくるのがホラー映画だと思うんですけども。その構造自体が逆転しうるものだと思うんです。

西尾:監督は階段も撮るのが好きですよね。
清原:あーそうかもしれません。
西尾:階段を印象的に撮る映画作家って小津安二郎、ジョン・カサヴェテスもそうですね。なんで階段を撮ることに惹かれるんでしょう?
清原:なんでだろう。