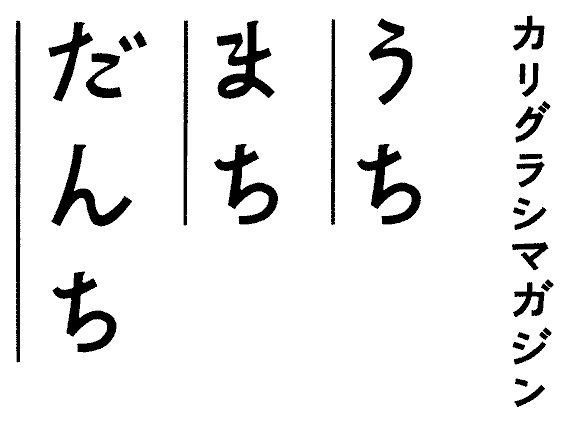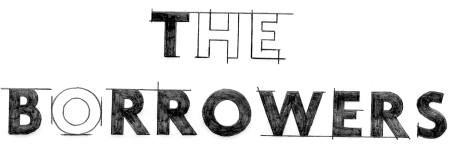長嶋有(作家)
長嶋さんの小説『三の隣は五号室』は、すこし変わった間取りを持つ木造アパートの一室を舞台に、そこに暮らした代々の住人の様子が語られるというもの。
いわゆる2Kの間取りに、13代の住人が暮らすことになるのだが、当然、彼らはお互いに顔見知りではなく、出会うこともない。それぞれの暮らしかたで何年かを過ごし、どこかにささやかなその痕跡を残したまま部屋を出て行く。つまり、50年間におよぶある部屋の歴史がパラレルに語られる、これぞ借り暮らし小説! という内容だった。
刊行後、『三の隣は五号室』は谷崎潤一郎賞も受賞。本作のことからはじまって、長嶋自身の住まい観や引っ越し歴などについて、たっぷりと語っていただきました。
長嶋有
1972年生まれ。2002年「猛スピードで母は」で芥川賞、2007年『夕子ちゃんの近道』で大江健三郎賞を受賞。主な著書に『三の隣は五号室』『フキンシンちゃん』など。
#1 引っ越しの場面、ただそこにある建物の話
『三の隣は五号室』は、50年間、13代の住人を見守りつづけた部屋が主人公のような小説でした。
長嶋:本の説明としては、「部屋が主人公」というのはぴったりなんだけど、書く側の意識としては、あくまでも舞台としか思ってない。6畳間が人格を持って話したりするわけじゃないから。
確かにそうですね。だけど、同じ部屋をいろんな住人が住み継いでいることを、こんなにも丁寧に書かれた話は読んだことがなくて。まず、引っ越しの場面も多く出てきますね。
長嶋:引っ越しは、僕も大学生で東京に出てきてから結構やったけど、その度ごとに似た景色を繰り返すんです。似た景色というのは、住む場所のことじゃなくて、不動産屋に会っていっしょに部屋を見てまわることとか、見知らぬ隣人に対する用心の仕方とか。あるいは、引っ越しを決めてから、ガス、電気、水道を止める連絡をすることだったり、引っ越した先で1日目にすることとかって、住む場所が違っても案外変わらない。「またこのやり取りをしてる」って思うことが繰り返し起こるじゃない。
引っ越しにまつわるあれこれは、確かに似たような過程の連続かもしれません。
長嶋:そう。でも、だから長い年月のうちに、ちょっとした微差も生まれる。「電話の加入料7万円の話はどうなったんだ」とかね。
ありましたね、高額な固定電話加入権。
長嶋:気づいたら光回線の話になってたり、そういう技術の発達とかで変わっていくことと、判で押したように変わらないものがある。これって小説で使えるなと思ったんだよ。
ものすごくささやかな話ですけど。
長嶋:これまで、自分が体験してきたことを織り交ぜて小説を書いてきたけど、だんだん“もう何も書くことないわ”って思いはじめるんです。自分の人生はほとんど使ってしまったから。だけど、それって本当かなと考えてみたら、不動産屋に相槌を打ってるとか内見のシーンとか、まったく小説にならないと思ってたところだけを集めたら、まだ使えるじゃないかって。料理のやり方を変えたら、三角コーナーに捨てていた魚の骨もまだ出汁がとれる、みたいなことですよ。
(笑)

長嶋:たとえば、別荘に誰かがやって来るみたいな外国の映画でも、その冒頭に一瞬だけ、内見するとか、家を借りるとか、「住み始めること」の描写があったりするじゃない。つまり、そういうことの果てに、主人公はそこに住むわけだから。多くの場合、それはプロローグで本編がそこからはじまるんだけど、その手前を本編にしてもいいんだよ。
引っ越しの場面を捨てる必要はないと。
長嶋:そうそう。それって普遍的に誰もがやることだから。遠洋漁業の人のことを書くよりも、みんながわかることのはず。だから、そんなに変な思いつきだとも思わなかった。
普遍的なことだからこそ、微差が面白く感じられるんですね。引っ越しの初日って確かにこんなだと思いながら、ささやかな個人差も生じてくる。
長嶋:引っ越し初日の盲点って照明器具がないことなんだよ。新居からはよりよい暮らしにしたいと思って、家具や調度を洗練させていくチャンスなんだけど、照明だけはその日の夜、真っ暗で過ごすってわけにいかない。だから、前の人の照明が残されてると、全然自分の趣味じゃないのに使って、そのまま使い続けちゃう。
うわーうちの家もしばらくそうでした。
長嶋:新居に似合った照明器具を1日目から持ちこめてたらいいけど、たいてい、ないんだな。だから、照明だけはちぐはぐな家が多い気がする。たとえば、そういうことが書きたかった小説なんです。

なるほど。
長嶋:それから案外、建物って忘れられたようにずっとそこにあるんですよ。別に愛されてるからじゃなく、重要無形文化財に指定されてもいないけど、でも、あるなぁと思って。チキンラーメンみたいに、“愛されて50年”というものばかりをみんな見たがるんだけど、ただそこにあるってだけの建物がたくさんある。
ほとんどの建物がそういうものですね。特に語られることもなくそこにある。
長嶋:そう。そこにあるんだから、その話は書けるだろうと。街のことにしても、デトロイトのように廃墟になって廃れる街がある一方で、今も昔も変わらず、ずっと人口10万人のままっていうような街もある。特にその街をみんなが好きだって意識があるわけでもなく、価値も変わらない。
淡々とそこにあるって、建物でも街でも一般的ですよね。ただ、それはやっぱりあまり話題にのぼらない。
長嶋:僕は、好きなものや愛着のあるものをモチーフにしたいという欲求が全然ないから。そして、何かに熱弁をふるうことで、「そのものが好きだ」と思われることが、意味がわからない。いや、こっちは熱弁ふるいたいだけですからって思う。興味はあるよ、語るんだから。だけど、好きかと聞かれたら、全然好きじゃないってこともあるはずで。何かフェティッシュな部分で、物語られてしまうことへの懐疑はすごくあります。
だけど、世間にあふれてる語りの多くはそっちですよね。
長嶋:『電化文学列伝』という、電化製品が出てくる小説の書評みたいな本を書いたことがあるけど、やっぱりすごく勘違いされて。「長嶋さん、家電好きですよね」って言われるんだけど、そうじゃない。決してマニアじゃないし、うちにある家電の数も他の人と変わらないはず。『三の隣は五号室』に関しても、別にあの家が好きというわけではないんです。
わかります。そういえば小説に出てくる最後の住人は、家にも街にも頓着なくて、「正負あらゆる印象が薄いこと」をこそ長所として考える人でした。その、とりたててどうということのない関係性や時間に目を向けるというか、そこをあえて語る優しさみたいなことを長嶋さんの小説に感じます。
長嶋:よく言えばそうかもしれない。だけど、表現ってそういうもんでしょう。写真を撮るってことを考えてみても、どうして他の瞬間じゃなくてその瞬間にシャッターを切ったのか。すごく突き詰めていくと、優しさみたいなことになるんだと思う。それしかないじゃん。

そうかもしれません。
長嶋:行きがかり上、撮ることもあるだろうし、需要があるから撮る、とかね。でもやっぱり、シャッターを押す瞬間には、それを何か肯定するような感じがあるはず…というか、肯定されてしまう。小説だって同じで、そこにただそれがあるということを書くだけでも、そのことを保存して伝えることになるから、やっぱり肯定されちゃう仕組みなんです。
ただし、それが必ずしも、対象に対するフェティッシュな愛情がセットになってるわけではないと。
長嶋:そういうことです。

『三の隣は五号室』(中央公論新社)
文:竹内厚 写真:鍵岡龍門