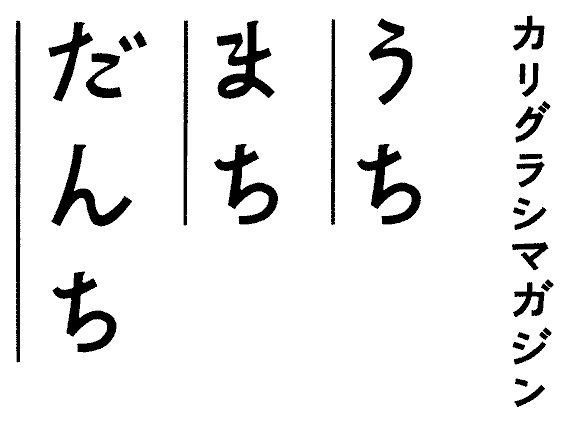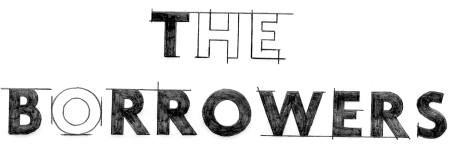長嶋有(作家)
#2 住まいに残された痕跡、コツについて
#1 はこちら
レバー式に取り替えられた水道の蛇口、延長されたアンテナの引き込み線、重いものが置かれていたらしい部屋の凹み、前の住人が残していったエアコンや蛍光灯…。『三の隣は五号室』では、かつて暮らしていた住人の痕跡のエピソードもたくさん出てきます。賃貸住宅のあるあるかもしれませんが、これもそんなに語られる機会のないことです。
長嶋:ほんとはそれだけで1冊書きたかったんです。ある住人は6畳間にテレビを置いたけど、ある住人は4畳半にテレビを置いてアンテナ線を伸ばした、とか。だけどやっぱりそれだけでは、書いてる方も退屈だった(笑)。さすがに、なんか出来事がないとなぁって。
だけど、残された痕跡に気づいて過去の住人のことを想像する人もいれば、まったくそこに気づかない人もいたり。歴代の住まい手それぞれの家に対する態度の違いが読者としては面白くて。そうだよなあと。
長嶋:レーシングゲームに、“ゴースト”っていうのがあるでしょう。過去に自分が1周59秒のラップタイムを出した、その時とまったく同じようにコースを走る半透明の存在と、自分が競争することができる。『三の隣は五号室』は、ひとつの部屋で、そういうゴーストが13人にまで増えていくような小説でしょ。つまり、全員が決して一緒にいたわけじゃない、けど、場所は共有していたという。書いてる側の意識としてはそういう感じ。
ゴーストのたとえ、言葉が怖いですけど、まさにそうですね。現実の家でもそこには代々の透明な存在がいる。
長嶋:実際の経験としても、前に住んでた人宛に郵便が届いたりして、気づくことがあるけど、それが劇的な体験ってこともまずない。間違って届いたダイレクトメールを見て、“ああ、ペン習字を習おうとしてたんだな”とか、あるいは、変なところにカーテンレールがついていて、なんでここにカーテンをつけて、何を隠そうとしたのかわからない、とか。

そういった前の住人のかすかな跡に対して、長嶋さんの気持ちは肯定的なんでしょうか。
長嶋:僕個人としてどこか清潔観念が薄くて、床に落ちたものでも平気で食べちゃうところがあるから。床の雑菌とテーブルの上の雑菌と皿の上の雑菌と、そんな差はないと思えてしまう。古本が汚れてるとかもまったく気にしないし。だから、残された痕跡に対して否定的に思えたことがないんだな。
そこの受け取り方、きっとかなり個人差ありますよね。
長嶋:そう、この本に関して山田詠美さんと対談した時に、登場人物の全員が前の住人の痕跡にわりと肯定的だけど、私だったらぞっとするって言われて。それは盲点だった。確かに、そういう住人がひとりくらいいないとおかしいよなって。
長嶋さんの性向みたいなところが、無意識にでも反映されているんですね。
長嶋:当然そうなるよね。ただ、僕が痕跡を見つけたとして、“わあ、うれしい!”って思うまでのことはないけど、でも、なんでこうなってるんだってことは考えるよね。これは別の小説で書いたけど、ホイールキャップが道ばたに捨てられてたから、道の脇に足でよけて通ったら、またしばらくしたら元の位置に戻ってて、なんでだろうと思ったら、雨の日にそこに水たまりができて、そのホイールキャップを踏めば水たまりを抜けられるんだって気づくんだよね。言語を介してないけど、その間に合わせの工夫に対しては、やっぱり肯定的に思いますね。「あのホイールキャップねぇ、うまいこと考えたもんですな」なんて、誰と会話することもできないんだけど。
痕跡には何らかの理由や必然があって、それが面白い。

長嶋:そうです。それは、室内だけに限らなくて、獣道にしたってそうなるだけの理由があるし、大規模な道路でも何かの理由で決まってできている。それが、間に合わせみたいなことでも、確かに僕は肯定的に思うんだよ。わかるよって。本当は、雨の日に水たまりができるなら、ホイールキャップを置くんじゃなくて、アスファルトを埋めたらいいんだから。横着ですよね。
そうか、根本的な解決にはなってないんですよね。
長嶋:そういった応急処置や横着とかに面白味を思うのは、僕の個人的なことだろうな。ちゃんとしろよって思うこともあるけど。
家に残る痕跡に少し似た話として、住まいのコツにまつわるエピソードもありますよね。障子を開け閉めするコツ、浴槽の元栓が水漏れしないコツ…。ニッポンはすなわちコツの国なんだと12代目の住人となるイラン人が実感する場面も出てきました。

長嶋:たとえば、障子襖って隔てる壁としての役目は、はなはだ脆弱じゃない? 隣りにいて聞き耳を立てれば聞こえるし、穴を開けたらのぞかれる。じゃあどうするんだっていえば、「聞き耳は立てないし、穴を開けないように使う」ってことだよね。人が障子襖のほうに合わせると、急にその用を果たすんだよ。
これは人から聞いた話で、別の場所でも語ってしまったんだけど、はじめてウォークマンを見た外国人が、「こんなツクリでは乱雑に扱ったら壊れちゃうじゃないか」ってウォークマンの技術者に言った、技術者は「だから、壊れないように扱うんです」って返答で。この問答がすごく好きなんだけど、落としたら壊れるから頑丈につくる、じゃなくて、落とさないように使えばいいっていうウォークマンが、結果、世界的なヒット商品になったように、たぶん、日本人はそういうのがうまいんだと思う。間に合わせ、みたいなことにも通じると思うけど。
物や住まいのあり様に対して気遣いをしながら、暮らしているということですからね。
長嶋:よく言えばね。だけど、頑丈につくることをサボっているとも言える。まあ、でも、iPhoneなんかすぐにガラスが割れるじゃん。割れてもなにか?って顔だし。むしろ、最近は日本のほうが頑丈かもしれない。
暮らしにまつわるコツ、これもやっぱり住まいの味わい方のひとつだとも思いました。
長嶋:そこまでポジティブなことかどうかわからないけど、記事的にはそうですねって言っといたほうがいいんだろうな(笑)。でもやっぱり、住まいのプライオリティの一番は、ただ住むということだから、痕跡やコツっておまけのようなものでしょう。

痕跡やコツというおまけのある賃貸暮らしと比べて、一軒家を持つことも考えますか?
長嶋:だけど、一軒家を所有して住むということのメリットの逆に、そこに住み続けなければいけないって不自由さは感じるよね。だって、100年しか生きられないのに。1000年生きられるんだったら、堅牢強固な要塞のような家を建てるかもしれないけど。一体、城をつくったひとって何年生きるつもりだったんだろうとは思う。人生50年っていうなら、借り暮らしのほうが楽じゃないのって。
そういった所有欲に対して何年生きるつもりなのってツッコミは、確かにありますね。
長嶋:まあ、いまは家でも車でも、買ったとしてもすぐに売れる仕組みが整ってるらしいじゃない。5年くらいたてば下取りにだして、最新のものに乗り換えていくって。そのことに対して、別に鼻白むわけでもない。僕だって、痕跡があるから、愛着があるから借り暮らしを選ぶと言えるまでのことはないから。メリットで判断して、売れると思えば買うかもしれない。それはわからない。
長嶋さんはずっと賃貸暮らしですか。
長嶋:それはそうなのよ。