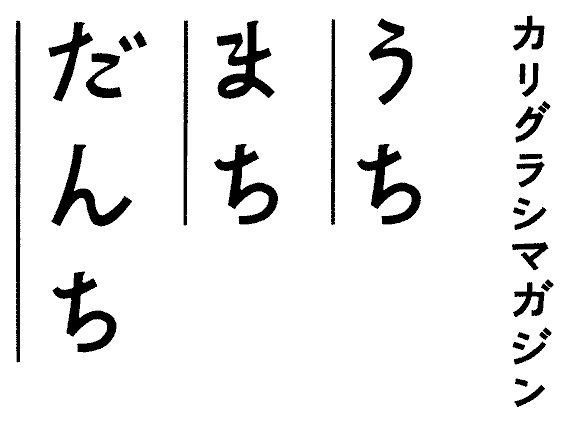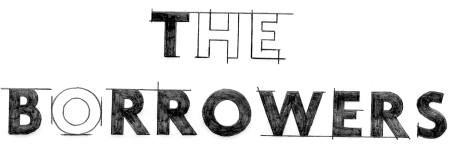富山の小さな文化施設LETTERを
始めた3人それぞれの理由
#3 アトリエセーべー・樋口裕重子さんの場合
気心知れた友人同士、あるいは、長年の幼馴染たちと一緒につくる場所ならいざ知らず、「初めまして」の3人が偶然出会ったことで生まれた、“LETTER”という場所。
一人ひとりが書く言葉は違っても、想いを届けたい相手にこの場所に来てもらいたいという気持ちは、3人に共通していました。
最後は、樋口裕重子さんから“LETTER”が向かっていく先を語ってもらいます。
#1 はこちら (風景と食設計室ホー・永森志希乃さんの場合)
#2 はこちら (ひらすま書房・本居淳一さんの場合)

これまで永森さん、本居さんから「いい距離感」という言葉が出てきたんですけど、同じ距離感で付き合える人が3人も集まったなんて、ちょっとした奇跡みたいなものじゃないですか(笑)。ちなみに永森さんとは古いお知り合いだったんですか?
樋口:いえ、実はこれもまた不思議な縁だったんですよね。
きましたね…。やはりここでも、“縁”ですか。
私、ここに来る前は富山市にある「フォルツァ総曲輪」っていう場所で、7年ほど勤務してたんですね。そこはライブホールとシネマホールのある公設民営のコミュニティスペースだったんですけど、そこでは銭湯の番台みたいな気持ちで、自分がいいと思ったものをお客さんに「とにかくこれ見てください」って言って、薦めてきたりしたんです。それでもやっぱり地方のミニシアターだと、集客が難しかったり、届けたい層に届かなったりするんですよね。
だから、とあるカナダの若手監督の作品が公開されるときに、映画文化にあまり触れないような若いお客さんにも響くようなイベントができないかなって思っていて、それでふと「ホー」のことを思い出したんですね。

じゃあ、ご存じだったんですね。
いや、勝手に名前だけ知ってました(笑)。いつか映画のワークショップ演出をお願いしたいなと思いつつ、経費もかかりそうだしなによりメールだけではコンセプトや想いを伝えきれないだろうなって。ただ“実らぬ恋”みたいなものかもしれないけれど、強く思っていれば必ず叶うんじゃないかって想い続けていたら、週に1回お店番をさせていただいている民芸店の店主に、「もう一人お店番をお願いする人を紹介したい」って言われたんですね。それが実は、永森さんだったんです。
え、どういうことですか(笑) そんなに簡単に、会いたい人に出会えるものなのか…。みなさん、結婚でいうところの“赤い線”以外の何物でもないですよね。
といっても、最初は同じく店番として紹介されただけだし、本人かどうかもわからなかった。でも、いただいた名刺に「ホー」と書いてあって、調べたら「やっぱりホーだ!」ってわかった瞬間、「えぇぇぇぇ? こんなことあるんだ?」って、本当にびっくりしましたね(笑)。そんな出会いもあって、とあるカナダの若手監督の新作が公開されるときに特集上映会とワークショップを企画して、「ホー」に“食べられるアート”としての映画体験を演出していただいたんです。きっとそういう経緯も含め、今回永森さんが声を掛けてくださったんじゃないかなと思いますね。それまで、ずっと観察してたんじゃないかな、私のこと(笑)。
観察ですか(笑)。

でも、そのイベントは永森さん自身が映画を観て感じたことを、彼女なりに咀嚼して“食”に置き換えて表現してくださったんですよね。何かを食べるイベントっていっぱいありますけど、誰かが咀嚼した表現を口にするって、あんまりないと思っていて。若い人も年配の方も、映画をあまり観ない人もミックスした空間が出来上がっていてとてもおもしろかったですね。
なるほど。ひとつの空間、同じ時間をいろんな人たちと共にするという意味でいえば、“映画”はある種、シェア文化みたいなものですよね。その文化の中にいた樋口さんなら、こういったシェアスペースに対しても、わりとポジティブだったんでしょうか。
うーん…、実は「本当に私でいいのか」って、永森さんとは何回も何回もやり取りしたんです。だって極端な話、お金を出せれば場所は借りられるとしても、本当に私のことをわかっていて貸してくださるのかって、そこを何度も確認しましたね(笑)。
だけど永森さん自身も、大家だからルールや規約をつくるということはなくて、私たちに任せてくれている。だからこそ、きっとうまくいくという確信が、最初からあったように思います。
みんなで言語化はされてないんだろうけど、空気感でお互いに伝わり合っている。
それってなんていうか、場所をシェアするとか、場をつくるみたいな小さな目標なんかじゃなくて、まさに“文化”を育んでいくという感覚なのかなって、思いました。
そうですね。私でいえば、デッサン教室を軸にしながらライブやトーク、オープンカルチャーみたいなことができたらいいなと思ってるんですが、やっぱりなんといっても、この場所自体に大きな力がある。だからこそ、「この場所で学びたい」と言って、通ってくれている地元の方がもう何人もいるんです。
ちなみにこの2階は、以前、電話交換手の方々が働いていたらしくて、「昔はこうでね」って地元の方が話してくれるのを聞きながらいろいろ妄想するのもすごく楽しいし。あ、窓もね、縦に開くこのタイプはもうないらしくって、窓枠がボロボロ崩れつつあるけど、それでもまだ使えるまではずっと使おうって、頑張ってます。

たしかに、1階と2階ではぐっと雰囲気が違いますね。ここだったら、重厚感のある空間で、なんだかデッサンもすごく集中できそう。
私のデッサン教室は、絵をうまく描くっていうより、よくモノを見るっていう時間って感じかな。最初はみんな、「絵を上手に描きたい」って言って来られるんですけど(笑)。でも、いろんなアートとか絵とかみせて「上手ってなに?」「どういうものが美しいと思う?」って問うていくと「よくわかんなくなってきた」ってなるんですよね。

デッサンは、見るっていうことをバラバラにしていくことであって、それはつまり考えるということ。その中で、ひとつでも「ハッ」となったら、もうその日1日はそれですごいことなんだよってお伝えしてるんです。
樋口さん、なんだかガイドみたいだなぁ。それぞれが自分の中に潜り込んでいって、自覚を引っ張りだしてくるための。
添乗員みたいな感じですよね(笑)。悲しかったこと、楽しかったこと、辛かったことっていうのは、感情の記憶としては残ると思うけど、でもそのときなにを想ったのかっていう感覚だけは、個人のオリジナルな感覚でしょ。だから私は、それを大事にしてほしい。子どもの頃は良かったじゃなくて、子どもの頃の感覚を操れるようになるのが大人なんじゃないかな。
だから、私のデッサン教室では、おじいちゃんとか子どもとか、お母さんとかそういう肩書みたいなものは全部外して、みんな、“ひと”っていう感じで接してます。
だからこそ、樋口さんのところに来たくなるのかもしれないですね。そして、この場所にあるこの空間だからこそ、何度も足を運びたくなる。

樋口さんのセンスでまとめられた空間は、なんだか映画のセットのように思えてくる。
たまたま私の場合は、デッサン教室という入り口ですけど、この場所は私だけじゃないんです。
永森さん、そして本居さんが持つ柔らかさやアプローチもとても大事だと思っていて、それがあるからこそ、ここに来る人の目的はみんな違ってていいんです。でも帰る頃には、また全然違うものに出会っているかもしれない(笑)。
目には見えないけど、いろんな“縁”がここには待っているんでしょうね。
昔の銭湯を例にとると、他人の背中を流してあげたり、子どもたちが走り回ってて知らない人に怒られたり、そうやって自然と何かを学んでいくようなコミュニティだったと思うんです。
だからこそ、ここに来ればいつもの自分から少し飛び出せるようなモノや人、コトに出会えて、でも一歩外に出れば、また日常の自分に戻っていける。そんな窓のような存在でありたいな、って。
それが、今までいろんなものをつないできた元郵便局という場所でできるなんて、なんだかすごくぴったりじゃないかなって、そう思うんですよね。

文:喜多舞衣 写真:山田康太
(2017年1月30日掲載)