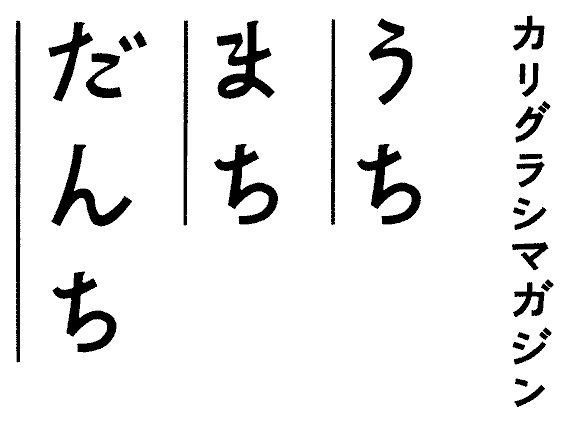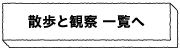2015.04.22
with
倉方俊輔(建築史家)
around
長堀橋~空堀~大阪城 〈大阪市〉
大阪市内ではそれほど数多くない、坂のある街を散歩中。目指すは本丸、大阪城へ!
#03
ガイドと案内板/歩道橋/復元された古代建築
―今日は暖かくて散歩日和ですね。
倉方:ほんとに。数日前までシカゴに行ってたんですけど、到着した日がマイナス12度で、帰国する日で10度くらい。短い期間で25度の温度差って大変でした。
―シカゴは建築の視察ですか。
大阪市が2013年から取り組んでいる「生きた建築ミュージアム事業」の推進メンバーと行ってきました。「シカゴ・アーキテクチャー・ファンデーション」という、ボランティア主体で街の建築ツアーを主宰している団体があって、そのヒアリングが一番の目的です。
―大阪もそれに学ぼうってことですね。
そう。シカゴでは、ボランティアが建築の解説をしてくれるんだけど、そのための試験もあったりして、みんなすごく勉強しているし、意識が高いんです。
―どうしても案内板だけでは頭に入ってこないから、大阪でもそうしたガイドがたくさん育てばいいでしょうね。
大阪にも見るべき建築はたくさんありますから。そして、語りかけることが大事。人が語るのもそうだし、案内板にしても誰が誰を対象にしているのかがはっきりしないから、なかなか伝わらない。
―今日もここまでいくつも案内板を見かけましたけど、倉方さんなしでは、読んでもその意味や意義がわからなかったかも。
建築関係の人でも、何年にできた建物だとか建築家が誰だとか、そういうデータを先に話しがちなんですけど、それだと「だからどうした」って話になりかねない。そうじゃなくて、建物のありようから話していくと、子どもでもわかる話になるんですよ。どうしてこの場所は気持ちがいいのか、どうして排除されてるような印象を受けるのか。その理由から考えていくと、建てられた時代の性格、設計者の個性、エリアの特徴、いろいろ見えてくるんですね。
―今日は、建築の見かたも教わっています。…谷町筋を越えて、ずっと坂を登ってくると一気に開けてきました。
大阪城が見えてきましたね。その手前が難波の宮か。古代の史跡にはあまり興味が無いのでスルーして(笑)…歩道橋を渡って、大阪城の方へ向かいましょう。
―歩道橋というのも渡る機会が減ってきました。
東京の原宿にも、東京オリンピックの時にできた歩道橋があったんだけど、最近、撤去されました。当時としては、車の流れを止めずに歩行者を通す、先端の技術でしたけど、やっぱりバリアフリーではないから。
―ここの歩道橋もスロープがありますけど、かなり遠回りになりそう。
あっ、向こうに高床式倉庫が復元されていますね。あれを見ましょうか。
―NHKと大阪歴史博物館のビルの前ですね。…あら、残念、復元された建物内には入れないんですね。案内板もミニチュアの復元模型さえも柵の内側に…。
建物を作るための予算はついても、管理費は出ないことから生まれる、公共施設のよくある形ですね。
―これだと教科書の資料集で見るのとあまり違いがありません。
中に入れない建物ってちょっと意味がわかりにくいですね。
大阪府警本部庁舎/壁の厚み/さりげないバリア
―NHKと道を挟んで立っているのが大阪府警本部庁舎。
倉方:これは黒川紀章建築なんですよ。2007年に没した翌年に完成した最晩年の作品ですけど。
―えっ、そうなんですか。変わった建物だと思ってましたが。
黒川先生は曲面ガラスが好きだから。同じく晩年に設計した、六本木の国立新美術館もそうですよね。あちらはもっとうねってますけど。ガラスを使っていても、決して軽くない、むしろ鈍重な…。
―それ、褒め言葉じゃない気がしますよ(笑)。
いや、女性的で軽やかな建築が主流になってきても、決してブレない。建築の男らしさを貫いたんです。権威を表現するために、わざと壁の厚みを見せたりして、施主の求めに率直に応えています。
―権威的というか、近づきがたい厳しさがありますね。
商業施設だったら、正面のガラス面をそのまま地上までおろしてきて、ウェルカムな雰囲気を出すんだけど、下は壁になってますからね。もう少し近づいてみましょう。
―…あっそういうことか、遠くから見ていると気づきませんでしたが、建物に近づくことすらできない構造になっているんですね。
緑を市民に提供しているようでいて、実は人を近づけない障壁になっている。今日の散歩のスタート地点で見た、ハトよけの針と意味は同じですね。一見、やさしい緑に見えるけども、実は…。
ーわれわれがハトだ(笑)。住友銅吹所跡にあったビルといっしょで、この建物も入り口がどこかわかりません。そして、きっちり監視カメラがこちらを向いています。
石垣を模したような塀のデザインもすごい。大阪城の前だから、お城っぽくして、未来感のあるデザインと共生…この見た目のわかりやすさ、黒川紀章の魅力がいかんなく発揮されてます。何がやりたいかよくわからない建築家の建物も多い中、この明快さが黒川さんの持ち味ですね。屋上には男の子が描く未来都市のようなヘリポートも! いいですね~。
円形の公共建築/使い方の問題/戦中のモニュメント
―制限時間ぎりぎりで、大阪城までたどり着きました。歩けるものなんですね。天守の周囲は大阪城公園として整備されていて、さすがに観光客が多い。
倉方:公共トイレと売店が一体になった現代建築が公園内で目立っています。建築家・遠藤秀平さんの設計ですね。コールテン鋼という、意図的に錆びをつけた素材を使いながら、なるべく軽く見えるよう、浮遊感のある建築にしています。
―黒川紀章とは目指す方向の異なる、軽快な建物ですね。
売店内の什器なんかも、もう少し考えられたらいいんですけどね。つまり、発注は建築家にしているけど、管理運営はまた別だから、逆に使いづらそうな状態になっている。
―使いづらいのは建築家のせいだと言わんばかり。
そうなんですよ。使い方次第なのに、すべてデザインが悪いことになるのは残念ですよね。視察してきたシカゴでも、中心部に20世紀を代表する建築家のミース・ファン・デル・ローエが設計した郵便局があるんですけど、24時間天井の明かりがともっていて、営業時間外にも建物がよく見えるようになっていました。優れた建築の存在が、訪れた人にシカゴという都市の格を伝えるんだという意識が感じられましたね。
―今あるものをいかに活用するか、という話ですね。
もしかしたら、ミースの建物だって、途中うまく使われていない時期があったかもしれない。でも、それを見直して、今ではうまく活用されています。世界を歩いて感じるのは、アジアにしても、ヨーロッパやアメリカにしても、近頃は世界中の都市が、すでにあるものをどうやって上手に見せたり、使ったりできるかという勝負だということです。大阪も、さらに気遣えばぐっと良くなりますよ。
―ゴールを前にして、話がどんどんまとまってきました。さすが!
それでは、大阪城を観察する前に教育塔だけ見ておきましょう。
―かなり巨大、だけど誰もかえりみないモニュメントが大阪城公園内にあります。
お城の周りって護国神社だとか、体制を象徴するようなものがつくられやすい。城自体が支配の象徴ですから。この教育塔は、1934年の室戸台風で教員が殉職したことをきっかけに、旧憲法下の教育体制を支えた教員たちを弔う目的で1936年に完成したもの。戦中の思想が反映された建造物なので、なかったことにされやすいんだけど、戦中にこの規模でつくられた塔って、実はもうあまり見られません。宮崎の高台に立っているアジアの遺跡のような「八紘之基柱」(あめつちのもとはしら。戦後の名前は「平和の塔」)とか、全国でも数少ない。
―巨大なので眼に入らないはずはないけど、この教育塔を観光している人はまず見かけません。
塔の前に柵があるので、近づけないようになっているのかと思ったら、実はトリックでしたね。柵と柵の間が開いていました。
―遠目に見る分には、まずわからない。やっぱり、あまり積極的に見てほしくないのかと勘繰ってしまいます。
日中戦争が本格化した1930年代には、満州やチベットのデザインが建築の世界で参照されるようになります。日本が島国じゃなくて、アジア一円につながる帝国だって表現をしたいと思った時に、当時、世界的に流行しはじめた幾何学的なモダンデザインにも通じるそれらも、「日本的なもの」として発見されるわけですね。この塔も、わざと大陸の建物に共通する細部デザインを選んで、それを抽象化しています。プロポーションは西洋の古典にのっとっていて、見事なまとまり。
―全然、日本っぽくは思えないですね。
そうそう。その日本っぽさというのは戦後の教育で、戦中の感覚だと、これこそがむしろ日本的なんです。大日本帝国的といいますか。そうしたことが敗戦と同時にがらっと切り替わりましたから。ここから導き出される教訓は、教育こそ疑わなきゃいけないってこと。
―教育塔を見て、教育を疑えという教えに!
規模の点からいえば、戦前の大阪の力がよく表れた建造物でもあります。大阪って、やっぱり一地方都市じゃないんですね。
→ 倉方俊輔さんとの「さんかつ#04」
のこる制限時間はあと少し。最後に大阪城の話で大団円!