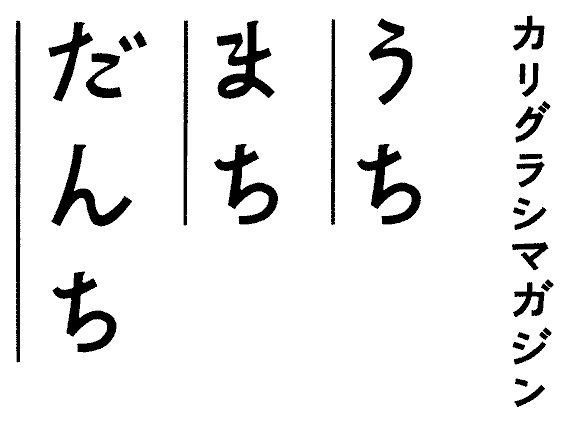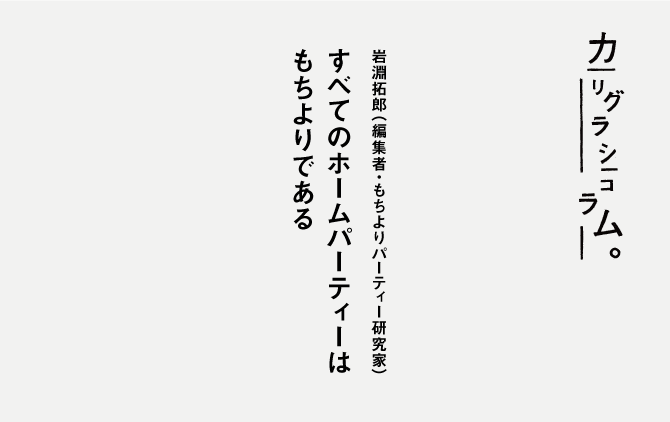「今日ちょっとパーティー行かなあかんねん」。
そんな誰かの何気ない言葉を聞くたびに、赤い眼鏡と白いスーツがよく似合うアメリカ人男性のことを想い出す。ミスター・ベーター。1995年から翌96年、ノリにノリまくっていたダウンタウンの看板コント番組『ごっつええ感じ』に登場した、人気キャラクターだ。ベーター氏は週末になると決まって知人が主催するパーティーへと出かけ、その行きしなにいろんな店に立ち寄っては気の利いた手土産を探す。ある時はパーティーに彩りを添える花束、ある時は口直しのスイーツ、ある時は子どもたちも一緒に楽しめるゲームなど。しかし残念ながら、おフザケが過ぎる店員のせいで、その計画はいつも失敗に終わるのだが……ドンドッドッド、ドンドッドッド、ってやかましわっ!!!
※お若い読者のみなさまは、YouTubeで「Mr.beter」と検索してください。
ミスター・ベーターの時代も今も、ホームパーティーには手土産がつきものだ。基本的に会費制ではないことが多いので、手土産はその代わりのようなものである。しかし何でも適当に持っていけばいいわけでもなく、どうせなら少しは気の利いたものをという心理が働く。ホスト側で料理を準備しているならやはりビールやワインなどが定番だが、コンビニ袋を下げて行くのも気が引けるから、わざわざ百貨店のリカー売場まで足を運ぶ。酒を飲まない人がいるならソフトドリンクも悪くないが、アルコールとの値段の釣り合いを取るため普段なら視界にすら入らない高級な瓶入りのものを選ぶ。女性が多いなら食後のスイーツも喜ばれるかもしれないが、他のゲストもスイーツを持って来た場合、そのまま冷蔵庫にしまわれて日の目を見ないという可能性もなくはない。
とにかく私たちは、その日のパーティーに関して知り得た情報――ふるまわれる料理の内容、ホストの人柄、パートナーや子どもの有無、家はマンションか一軒家か、他に招かれているのは誰か、男女や年齢の比率など――から、もっとも気が利いている手土産が何かを推測することになる。いや、もしかすると、手土産だけでは飽き足らず、会話が途切れたタイミングでさりげなく披露する気の利いた小話や、突然の「なんかいい曲かけてよ」にもスマートに応えるSpotifyの気の利いたプレイリストなども、さり気なく仕込んでいくかもしれない。
さらに言えば、そうして気を利かせて持ち寄ったあれやこれやが実際に気が利いたものになるかは、パーティーが始まってみないとわからない。手土産が他の人とかぶるほど最悪なことはないし、気がつけば全員が示し合わせたようにいなり寿司を持ってきた(実話)なんてこともある。小話や音楽にいたっては、そもそもそれらを披露するタイミングがあるかどうかも疑わしい。めんどくさいったらない。
なぜ私たちはホームパーティーに、これほどまで気の利いた何かを持ち寄ろうとするのだろう。こうした無意識のプレッシャーがゲスト側にもホスト側にもそれなりの負担をかけていることは明らかだ。ならばいっそのこと会費制にして、手土産は禁止にした方がいいのではないか。ホストとゲストの間で金のやり取りをすることが無粋だと言うなら、酒も食べ物もケータリングにして割り勘にすればいいのではないか。そうなれば、そもそもホームパーティーである理由すら微妙なので、レストランやホテルの宴会場を借りてやればいいのではないか。しかしそんなパーティーは誰が何のために主催し、参加するというのだろうか……。
ちなみにミスター・ベーターがパーティーを渡り歩いた1995年当初は、まだパーティーと言えばホテルや会館などを借り切って行われる立食形式の祝賀会や謝恩会が一般的だった。そうしたパーティーは、主催者もしくは参加者がそれなりの金額を払うことで提供される、いわば上げ膳据え膳の環境だ。もちろん気の利いた手土産などを持ち寄る必要は一切ない。私たちはただ提供される環境の中、その場と調和の取れた体のいい装いで、配膳係が運んでくるシャンパンやチーズが乗ったクラッカーをつまみながら、主催者としてのメンツを誇示するべくVIPと握手を交わしたり、新しいビジネスパートナーを探し当てるため誰彼構わず名刺を配りまくったりすることができる。そして帰り道には、今日のパーティーは飯がまずかっただのロクな出席者がいなかっただの文句を垂れることができるのだ。同じく95年に出版されたサントリー不易流行研究所編『パーティーと宴会 集いの日本文化』(都市出版)には、当時の立食パーティーへのじくじたる思いが赤裸々に綴られている。
“最初の挨拶や乾杯はまあ辛抱しよう。そのあとが問題だ。たいていの立食パーティーでは、あとは人と話をするか食べるしかない。人と話すと言ってもたいていは知った顔を探すのがおちである。(略)食べることも問題である。日本人は比較的しっかり食べる傾向が強いから、飲み物と皿と箸を持って、立ったまま食べるということを強行するが、これが快適ではないのである。(略)パーティーの途中でスピーチが入ることもあるが、これも最低である。”
※ちょっといやらしい引用をしてしまいましたが、良書です。日本のパーティーの成り立ちなどに興味のある読者はぜひご一読を。
金を払って提供されるパーティーと、参加者が気の利いた何かを持ち寄ることで出現するパーティー。これらは同じ「パーティー」でありながらまったく別の方向性を持った集いである。どちらが良いとか悪いとかいう話ではない。ただもしあなたが週末の友人宅で、気心の知れた友人たちと一緒に、手料理を味わったり他愛もないおしゃべりを楽しみたいのであれば、やはり気が利いた持ち寄りは欠かせない。たくさんの「気が利いた」が持ち寄られるパーティーは、やっぱりとてもいい気分なのである。
なお、少し余談になるけれど、ここ10年ぐらいやたら耳にするようになったソーシャルやコミュニティといった界隈では、持ち寄りそのものが集いの手法として用いられることが多い。彼らは、前述の立食パーティーほどではないにせよ、彼らの言うところの「集いの創出」という目的を掲げていて、そのきっかけとしてお薦めの本だの社会を良くするアイデアだのを持ち寄る。OK。確かにそれらは持ち寄りのハードルを下げ、参加者の自尊心を満たし、実際にプレゼンテーションのツールとしてもよく機能するかもしれない。しかし、それらはおおむね自己完結していて、あまり気が利いているようには思えない。そもそも「私はこんな人間ですよ」と言わんばかりにお薦めされた本を読む人はまずいないだろうし、ましてや社会を良くするアイデアなど実現されるはずもない。そしてなによりそんな気が利いていない持ち寄りが集まるパーティーは、いつもどこか色気を欠いていて、パッとしないのである。
と言うものの、やっぱりパーティーに気の利いた何かを持ち寄ることはそれなりに悩みの種だ。そこでひとつ、この8月23日に若くして亡くなった大阪出身のデザイナー・森口耕次君が考案したあるホームパーティーのアイデアを紹介したい。もしあなたの家にオーブンがあるならば、友人を招いてピザパーティーを主催してはいかがだろうか。ホストであるあなたが用意するのはピザ生地とピザソース、そしてゲストが持ち寄るのはその上にのせる具材だ。ピザの具を持ち寄るというテーマは、選択肢が狭いようで意外と自由度が高く、実に選びごたえがある。ネットで輸入物の高級食材を取り寄せるのもいいし、近所のスーパーでおおよそピザの具にはならなさそうなスナック菓子や缶詰を買って持って行くのもいい。そして、何をどう乗せて焼くかはその時々でみんなでわいわい言いながら決める。ピザというのは不思議な食べ物で、だいたい何をどう乗せてもそこそこ美味いし、たまに意外な組み合わせが奇跡的な美味しさを生み出すこともある。それぞれが持ち寄った気の利いた具材を、みんなでよってたかって気の利いたピザにする。森口君はこのパーティーに「編集ピザ」という、少々面白みに欠ける名前をつけたけれど、もちよりパーティーのアイデアとしてはやっぱり秀逸だと思う。
岩淵拓郎
1973年、兵庫県宝塚市出身/在住。屋号はメディアピクニック。2002年から美術家として活動(2011年に廃業)。現在は文化・芸術関連の本や冊子の編集、地域や子どもの文化プロジェクトの企画・制作、ものづくり系企業のブランディングなど。主な編著に『内子座~地域が支える町の劇場の100年』(学芸出版社/愛媛出版文化賞)。2011~14年、宝塚映画祭総合ディレクター。一般批評学会所属。趣味は旅と料理。
https://mediapicnic.tumblr.com/