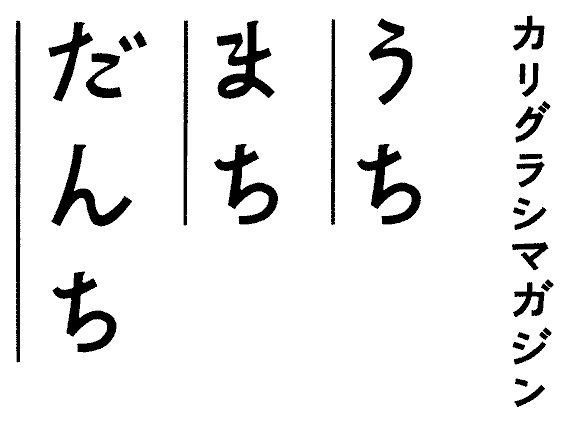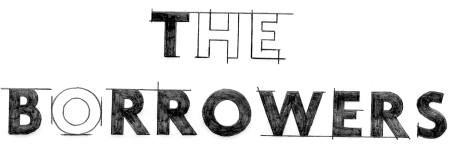阪急うめだホールで行われた『UR ひと・まち・くらしシンポジウム
』。街や団地でそれぞれに注目の活動を行っている面々が顔を揃えました。
ディスカッションの中で飛び出した注目の発言を再編集してお届けします。
出演者
パネリスト:岸本千佳(株式会社アッドスパイス代表取締役)、アサダワタル(文化活動家/アーティスト/大阪市立大学都市研究プラザ博士研究員)、千葉敬介(東京R不動産/『団地のはなし』編集)、西山直人(UR都市機構)
司会:竹内厚(OURS.編集者)
団地のバッファとコミュニティ、
ゆるくなってきた今こそ
千葉:仕事で団地のことをやってますと言うと、「団地とマンションの違いって何ですかね」という質問をぶつけられることが多いんです。そこで思うのは、団地には“バッファ”があるということ。玄関を出てすぐ公道じゃなく、自分のスペースでもあり、隣りのスペースでもあり、みんなが自分のものだと思っているような、そんな共用スペースを通って外へと出る。そこが団地の魅力だなあと思っています。
アサダ:たとえば、集会所や組合って、どうしても新しい人は入りづらい面もありますよね。コミュニティというのは、できあがってしまうと風通しが悪くなるところもあって、だけど、コミュニティができないことには次の流れにも行けない。そこはイタチごっこみたいな感じがします。
団地のコミュニティでも当てはまりそうな話ですね。
アサダ:だから、参加してみたけど「ちょっと違うな」って感じた人が、あきらめてしまうんじゃなくて、別のコミュニティに入り直せたらいいなと思います。そのためには、集会所のようなひとつの中心があるというよりも、複数のコミュニティがいくつか並行して活動しているような状況をどうつくれるか、それはいつも考えるところです。
ひとつの核よりも、小さな無数のコミュニティが同時並行で存在しているようなこと。
アサダ:そうですね。僕は前に住んでいた滋賀県の大津市で、町内会に入って役員をやってました。良くも悪くも町内会があるからできることがたくさんあるし、町内会がメジャーな存在で、それ以外は“オルタナティブな何か”という存在になる。でも、そのオルタナティブな何かが町内会だけでは満たされないところを補っているんです。
団地住まい経験のある岸本さん、どうでしょう。
岸本:団地には余白がたくさんあります。住むための建物以外のもの、それがコミュニティのための場だったりするかもしれませんが、そういったものがつくりやすい環境だなとは思います。
バッファ=余白や共用部があって、自治会をはじめとするコミュニティ活動もあって。確かに、それが団地だと思いますけど、果たして団地に暮らす人たちがどの程度、そのことに気づいているか、機能しているか。
千葉:団地の自治会って、団地ができた当時はスクラムをがっちり組んで、みなで同じ方向を向いてっていう、世の中もそういう時代だったこともあって、それができたんだと思います。だけど今、自治会の方を取材すると、「もう35年やってます」みたいな方が多くなっている。結果的に、かつて強固だったスクラムは、もうゆるゆるになってきていて、それが今、むしろいいなって感じています。
ゆるくなってきたのが逆にいいと。
千葉:僕のようなおっさんが入っていっても、まだまだ子ども扱いだし、そのスキマや立場をうまく使えば、ぬるっと面白いこともできる。それでいて、「あの人に言えばみんなに伝わる」といった自治会ならではの機能もまだあるから、そこを活用して。さらにいえば、あと10年もすればそれはなくなってしまうかもしれないですし。
自治会歴35年という経験者がいなくなるし、自治会さえも存続しているかどうか。
千葉:だから、今のうちにうまく使って、面白いことを実現させていけたら、その機能を継承していけるんじゃないかなって思います。
アサダ:それは僕もあると思います。担い手が減っている分、若い人に対するトビラも開いているし、一緒にやれることがすごくあるなと感じます。
岸本:その延長線上で、私がもうひとつ気になっているのは、団地の住人が団地を去るときのことですね。実際に、昨年、おなじ団地に住んでいたおじいちゃんが亡くなったんですけど、その今はひとりでいるおばあちゃんから私に手紙をいただいたことがあるんです。
血のつながりはないけど、同じ団地に住む老夫婦とのおつきあいですね。
岸本:そうです。自分の親族ではないけれど、とても身近に感じられる存在で。そこは、まだうまく言語化できてないですけど、何か寄与したり、考えることができないかなというのは自分のテーマのひとつだと思っています。
(次のページへつづく)団地から去る、見送る。確かに、そこにもいろいろ考える余地がありそうです。