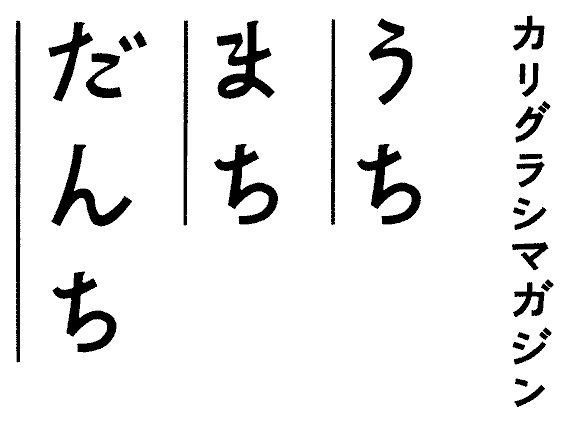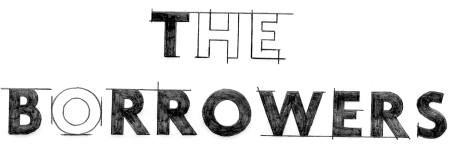大家さんと賃貸住宅、まちの話
青木純(大家/都電家守舎)
青木純さんが、祖父の代から続くマンションの大家業を継いだのが2011年。空室率30%に近づいていたという、その中古マンション「ロイヤルアネックス」を自由なアイデアと仕掛けで、“行列のできる賃貸マンション”へと再生して、青木さんは新時代の大家さんとして一躍、時の人となりました。
その後、青木さんの活動はロイヤルアネックスだけに留まることなく、8世帯の共同住宅「青豆ハウス」や、北九州から全国に広がる「リノベーションスクール」など、賃貸住宅からまちづくりにまで及んでいます。
賃貸住宅の革命児が考える大家さんのあり方、団地の未来。
ロイヤルアネックス2階に作られたシェアスペース「co-ba」に場所をお借りして、青木さんの話をたっぷり聞いてきました。
青木純
1975年生まれ。カスタマイズ賃貸の第一人者として知られる。賃貸マンション「ロイヤルアネックス」、共同住宅「青豆ハウス」などを運営。都電家守舎の代表として、都電荒川線沿線のまちづくりにも取り組む。著書に『大家も住人もしあわせになる賃貸住宅のつくり方』(学研パブリッシング)。

#1 青木さんから団地への提案
先に団地のことからお聞きしてもよろしいでしょうか。今、青木さんは団地に対してどんなイメージを抱いていますか。
青木:豊かな共用部があって、コミュニティを作りやすい住宅という感覚ですね。
昔からそう思われてました?
青木:いや、大家業をはじめてからですね。その前は、団地って無個性だなぁと(笑)。僕はもともと、賃貸住宅なんて無個性な場所には住みたくないと思っていたんです。ロイヤルアネックスを大家として引き継いだときも、住みたいかといえば正直、微妙な感じも(笑)。
賃貸は好きじゃなかったが出発点だったとよく話されていますね。それが今では、いろんな賃貸住宅の可能性を見出されています。

青木:そうですね。たとえば、住まいにおける情緒的な部分ってすごく大事だと思うんですけど、団地の情緒性は、一般の賃貸に比べてとても高いと思います。多様な世代が住んでいることもそうだし、わかりやすくお隣さんの夕食の匂いだとかね。是枝監督が映画に撮っていた世界観そのまんまですよ。団地って個別に分けられているようでいて、分かれていない。階段、廊下は共用、ダクトや排気口もすごく近くにあって、匂いはもちろん、ある意味で生活の音も共有しているところがある。それだからいいという面もあると思います。
それだから悪い、じゃなくて。
青木:悪くない。こんな時代だからこそ、それはすごく豊かさの象徴になりえます。ゴミ出しをして、「あっどうも」って出会ったり、あの人いつもあの時間に家を出るなーとか。見るともなく互いの生活が見えてしまうところがいい。特に賃貸住宅の場合、プライバシーとセキュリティの面からどんどん戸別に断絶して、境界をはっきりとさせてきましたけど、やっぱりそれでは面白くないんです。小さな空間に閉じても生活がつまらない。それに、隣人の顔がわからないことってとても不安ですよ。

東池袋にあるロイヤルアネックス。
そうした不安が自然と解消されるくらい、団地は隣人の距離が近いといえますね。
青木:僕がロイヤルアネックスの大家をしていても、顔が見えないことの不安ってあるんですね。大家といっても、親から引き継いだ“雇われ大家”みたいなものでしたから、最初はひとりも顔のわかる住人がいなかった。だから、新しく部屋を見に来られた方には、「じゃあ、お名前とお仕事から教えてください」ってほんとに面接みたいな時間を設けています。“えっ、ただ部屋を見に来ただけなんだけど…”って、はじめは、みなさんキョトンとされて。
びっくりされるでしょうね。
青木:今ではだいたい1回のご案内で、1時間から1時間半くらいの時間をとるんですね。ちゃんとお話をしてから、まずは屋上へお連れして、住民で共有している屋上菜園「ソラニワ」の話からコミュニティのこと、周辺のエリアの説明をして、「じゃあ、そろそろ部屋に行きましょうか」って。場合によっては、他の住民と出会って立ち話をしたり、管理清掃を担当している今井さんってマンションの名物おじさんをご紹介したり。最後に、ここでの暮らしぶりを少しでも体験してもらいたいから、「都電テーブル」*で食べてってくださいねって。

都電テーブルは、ロイヤルアネックス2階に昨春オープンした食堂。
もはや、「ロイヤルアネックス」ツアーですね!
青木:そこまでコミュニケーションをとればまず大丈夫です。それに、事前にきちんと話をする方が結局は楽なんですよ。だから、悪いことも正直に言いますよ。「前の春日通りはめっちゃうるさいですよ」とか。“これくらい大丈夫”って言われても、「いやそうは言っても、夜中に消防車が通ると音がすごくて…」と食い下がったりして(笑)。実際、古い建物だからスペックも落ちてるし、畳が沈むことだってあるかもしれない。当然、住んでみないとわからないことの方が多いけど、なるべくそのギャップがないように、ですね。

ロイヤルアネックス屋上からの眺め。夏はここから隅田川花火大会を見るのが住民の恒例行事。
部屋の内見というのは、大家さんにとっても、住むことを考えている人にとっても、建物とお互いを見る大事な機会なんですね。まさしく面接。
青木:そうなんです。だから、最初に話をしていて、あまりピンと来てないなという方は、そんなに部屋も見ないで帰られますね。今はもう、ここ(ロイヤルアネックス)での取り組みに共感した上で来てくださる方ばかりなので、実際にここに住んで楽しんでもらえそうかどうかという、感覚的なところだけ見れば大丈夫になってきてますけど。
大規模な団地だったとしたら、そこまでの細やかなやり取りをするのは難しいでしょうね。
青木:そうですね。ひとりの大家として、がんばって顔が見えるのは100世帯まで。まあ、200世帯も見れたらすごいなというのが実感ですから。
今では、URの中にもお友達がたくさんいるので、内部の苦労もよく知っていますし、大きな組織だから意志決定は難しいだろうなと思います。ただ、大家としてのURは圧倒的に存在感があるのは間違いない。横から見ている分には、それほどまだ色を持っていないかなと思うので、決断を持って動きはじめるとがらっと変わってくるんじゃないかな。
壁紙を自由に選べるところからはじまったロイヤルアネックスの取り組みと同じく、URでも自由に壁に手を入れられる「カスタマイズUR」などのプロジェクトが動いています。
青木:それも当初からご相談を受けていましたけど、URであればやっていけると思っていました。そこは、単にトレンド的なツールとしてDIYを使ってしまう民間の賃貸住宅とは違って、URは大きなうねりをつくれる存在じゃないですか。ただ、DIYやカスタマイズって、あくまでもキッカケだと思うんです。部屋を居心地よくするための入口であって、それから先、住まい手自身が次の住まい手に受け継ぐような形で、仕上げていってくれるところに価値があるんじゃないかって最近は思っています。

ロイヤルアネックスに暮らす宮田サラさんの部屋。壁紙を自由に選んだ「カスタムメイド賃貸」の一室。
部屋のカスタマイズやDIYの他に、団地でさらにできそうなことって何でしょうか。
青木:コミュニティコーディネイトはまだまだやる余地がありそうですね。そういったことが一緒にできる住まい手を育てて、団地ごとにその文化を根づかせていくってこと。団地に限らず、そういった取り組みを始めているところはあるんでしょうけど、実際、なかなか続かないんですよね。
文:竹内厚 写真:平野愛